地代の増額について
ここ数年、全国的な地価上昇が続いており、特に都市部でこの傾向は顕著です。
地価上昇は、実際の取引価格が先行して上昇し、これに連動して毎年の相続税路線価、公示地価、基準地価、3年に一度の固定資産税評価額など、すべての公的地価が上昇します。

賃貸経営は、公的地価の上昇に影響をうけますが、特に貸宅地の場合は大きな影響を受けると言えるでしょう。
固定資産税評価額が上昇すれば、当然、固定資産税、都市計画税も上昇しますので、これまでの地代水準では、地代から固定資産税等を差し引いた収益が低くなります。したがいまして、多くの地主は地代の値上げを借地人に申し出ますが、「ハイそうですか」といってくれる借地人ばかりではありません。
地価上昇の実感がわからず、土地の固定資産税を直接支払わない借地人にとっては、生活に直結する地代の値上げは深刻な問題です。
特に平成バブル崩壊から地価下落の時代が大半を占め、長きにわたって地代の増額改定を経験したことのない借地人には一大事です。なかには地代水準についてインターネットなどで調べたり、専門家と称する不動産会社や、弁護士、司法書士、税理士などに聞いてみたりして、自分に都合の良い情報をとり入れ、いかに地代が高いか、増額改定が不条理かを地主に説いてくる借地人もそれなりに存在します。
地代の算定方法については特にルールがある訳ではありません。固定資産税の倍率であったり、路線価などの公的価格であったり、周辺取引事例であったり、収益還元であったり、これでなければならないというものではありません。高くしようと思えば、高くするための理屈がありますし、低くしようと思えば低い理屈をいくらでも並べられます。
特に弁護士などの法律家に相談すれば、弱者救済という名のもとに、地主はけしからん、適正と思える地代を供託すればよい、などという無責任なアドバイスをするのは目に見えています。
もちろんこれらは借地人に認められている権利ですので悪い事ではありません。しかし、地主にとってみれば、権利や理屈をならべて、いかに地代の増額改定が不条理であるか説かれても、多くの地主は、「ハイそうですか」という事になりません。
地代の改定に限らず、借地の更新料や、譲渡、建替えの承諾に伴う承諾料も特に算定ルールはありませんので、専門家に相談すれば、安くする理屈はいくつでも出てきます。こうもなると、地主は、権利主張ばかりして面倒くさい借地人だと思い、譲渡や建て替えなどの承諾は考えた方が良い、またはそれなりの承諾料を請求しようと考え、今後の借地関係に支障をきたすことが想定されます。目の前の地代や更新料、承諾料を安くするために、結果的に肝心の借地権という財産価値を毀損させてしまうということがわかっていないのです。
要するに、何事も感情の伴う人間同士の話し合いです。あれこれと理屈を並べたてるより、お金がないのでもう少し安くしてもらえませんか、と頭をさげたほうが円滑にまとまるケースがほとんどです。地主の皆さんも、頭を下げられたら少しは考えてあげてください。
(著者:不動産コンサルタント 伊藤)
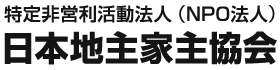

 03-3320-6281
03-3320-6281
