第6回 敷金の基本ルール
1 はじめに
借地・借家契約を締結する際、賃借人から賃貸人に敷金を差し入れることが一般的ですが、今回は、敷金の意義や基本ルールについて確認したいと思います。

2 敷金の意義
敷金とは、「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭」とされています(民法第622条の2第1項)。つまり、賃借人の金銭債務を担保するために差し入れる金銭を意味します。
一方、「保証金」の名目で金銭を差し入れることもありますが、保証金については民法の規定はなく、その意義は必ずしも明確ではありません。もっとも、一般的には敷金と同様のものとして扱われており、その場合は保証金の名目であっても基本的には敷金に関するルールが適用されることになります。また、契約内容によっては、保証金が「建築協力金」や「権利金」の性質を有する場合もあります。
3 敷金の基本ルール
⑴ 敷金の返還時期
賃貸人は、①「賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき」、または、②「賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき」は、賃借人に敷金を返還しなければなりません(民法第622条の2第1項)。
⑵ 返還前の弁済充当
賃貸人は、敷金の返還時期の前でも、敷金をもって未払賃料等の弁済に充当することができるとされています。一方、賃借人の方から充当を請求することはできません(民法第622条の2第2項)。
⑶ 返還時に控除できる金銭債務
賃貸人が敷金を返還する際には、賃借人の賃貸人に対する金銭債務を控除した残額を返還することになります。ここで控除することができる金銭債務には、賃借人の未払賃料のほか、用法違反等による損害賠償金、契約終了に伴う原状回復費用等が挙げられます。
なお、建物の原状回復費用については、通常損耗・経年変化以外の損傷(賃借人の故意や不注意により生じたもの)に関するものは賃借人の負担であるため敷金から控除することができます(詳細については、令和3年11月号の本コーナーをご参照ください)。
⑷ 賃貸物件が譲渡された場合の処理
賃貸借契約の継続中に、賃貸人が第三者に賃貸物件を譲渡した場合、基本的には賃貸人たる地位が譲受人に移転しますが、それとともに敷金関係も譲受人が承継することになります。したがって、賃借人は、譲受人(新賃貸人)に対し、敷金の返還を請求することができます。
⑸ 敷引特約
賃貸人が敷金を返還する際に、あらかじめ取り決めた金額を差し引く旨の特約(敷引特約)が契約書に定められていることがあります。判例によれば、事業者と消費者との賃貸借契約に関する事案について、敷引特約が通常損耗等の補修費用を差し引く趣旨であることを前提に、当該費用として通常想定される額や賃料の額などに照らして敷引金の額があまりに高額である場合は、特段の事情がない限り、消費者(賃借人)の利益を一方的に害するものとして、消費者契約法に反し無効になると解されています。なお、判例では敷引金の額が賃料の3.5倍程度の事案について敷引特約が有効とされているため、この金額が一つの目安と言えるでしょう。
4 まとめ
敷金の意義や基本ルールについては、令和2年施行の改正民法で明文化されましたが、従前の取扱いから大きな変更はありません。もっとも、敷引特約については、敷引の可否・範囲を巡って争いになる可能性がありますので、契約書に定める場合は注意を要するところです。
(著者:弁護士 戸門)
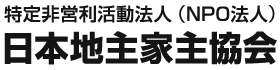

 03-3320-6281
03-3320-6281
