見た目が変わると本質が見えづらくなる
世の中には多くの投資商品、節税商品と呼ばれるものがあります。
当然、投資にはリスクが付き物ですが、中には、少し複雑でよくわからないという商品や、リスクというよりそもそも詐欺に近いのではないかと思われるものもたくさんあります。
では不動産にはどのような投資商品、節税商品があるのでしょうか。

最近耳にすることが多くなりましたが「不動産の小口化商品」という投資、節税を併せ持ったという商品があります。
特徴は、比較的少額で投資できる、それなりの配当が得られる、相続税の節税効果が見込める、という触れ込みで、それなりに売れているようです。
要するに、複数人共同で収益不動産を購入し、その共有持ち分に応じて賃料を分配するという投資商品です。所有形態は不動産の共有ですので、税金の取り扱いは不動産の現物を保有しているのと同じです。相続税の評価上は土地は路線価評価、建物は固定資産評価、加えて貸家建付地の評価減が適用され、購入(出資)金額より低くなり、相続税の評価引き下げ効果があると言われています。
投資の単位は1口1千万円程度で、不動産投資にしては確かに少額ではあるのですが、その出資持分(共有持ち分)が1千万円の価値があるかどうかは判断の難しいところです。
出資持分の価格の考え方は、その対象となる収益不動産の価値を出資口数で割ったものです。そのように考えると対象となる収益不動産の客観的な価値と、小口化された出資持分の合計は限りなく一致しなければなりません。しかし、現実は出資持分の合計が収益不動産の客観的価値を上回るような商品設計が多く見受けられるようです。マグロ1本の値段と刺身の合計の値段の違いと考えればイメージがつくでしょうか。
もちろん不動産の価値は絶対的な指標が決められていないため、人によって、考え方によって価格は異なりますが、うがった見方をすれば、収益不動産単独で売却するよりも、小口化にして細かく分けた方が結果的に高く売却できるという、頭のいい売主が物件を高く売却するために考案した方法とも言い換えられます。
例えば年間収入4000万円の収益不動産を単独で第三者に売却する場合の客観的価値が10億円(利回り4%)という収益不動産を年間配当20万円、1口1000万円(利回り2%)という商品設計にした場合、理論的には20万円の配当をベースに200人に売却することが可能となりますので不動産の客観的価値は1000万円×200人で20億円と、単独で第三者に売却する場合の2倍になります。これは分かりやすく計算した例ですが、これが売主側、商品供給側の儲けのカラクリです。
前述しました通り、不動産には絶対的な価値基準がないためこのような考えが良い、悪いということよりも、それが1千万円の価値があるのかよく考えようということです。小口化商品の相続税の評価引き下げ効果にしても、実際の換金価値があって初めて成り立つ引き下げ効果ですので、そこだけに着目しても本質を見失ってしまします。
(著者:不動産コンサルタント 伊藤)
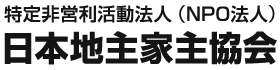

 03-3320-6281
03-3320-6281
