第1回「相続登記義務化~その1」
今回からは「これからの相続・遺産分割」というテーマで1年間連載します。初回の今回は、昨年(令和6年)4月1日施行された「相続登記の義務化」についてお話しします。
【不動産(土地・建物)の相続登記が義務化されたのはなぜですか?】
相続登記がされないために、登記簿を見ても所有者がわからない「所有者不明土地」が全国で増加し手います。その面積は、九州の面積に匹敵し、また、不動産登記簿のみでは所有者の所在が判明しなかった土地の割合は24%にも及びます(令和4年度国土交通省調べ)。そのため、周辺の環境悪化や公共工事の阻害などが生じ、社会問題化しています。
この問題の解決のため、令和3年に法律が改正され、上記のとおり、令和6年4月1日からこれまで任意であった相続登記が義務化されることとなりました。

【相続登記の義務化とは、どういう内容ですか?】
相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になりました。相続登記は法務局に申請する必要があります。ここで注意すべき事は、「相続開始(死亡時)から3年以内」ではなく「不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内」という点です。つまり、起算点が、相続開始時(死亡時)よりも後であることもあり得る(死亡後、相続人が調査をした結果、相続の対象となる不動産があることが判明した場合)ことになります。
更に、遺産分割協議で不動産を取得した場合も、別途、「遺産分割の成立日から3年以内」に、相続登記をする必要があります。
一方、正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。なお、「過料」とは、行政法上の罰則で、刑法などで定められる刑罰には該当しません。従って、「過料」の場合は前科はつきません。
【義務化が始まった令和6年4月1日より前に相続した不動産については、どうすれば良いですか?】
このような場合も、相続登記がされていないものについては、義務化の対象となり、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります(3年間の猶予期間)。
【相続登記申請の方法はどのようなものがありますか?】
相続登記申請の方法は、
①登記名義人からの特定財産承継遺言又は遺贈によって所有権を取得した相続人が相続登記申請期間内に登記をする場合、
②単独相続した相続人が、上記期間内に登記をする場合、
③共同相続人らが遺産分割協議を行い、それによって不動産を取得した相続人が上記期間内に登記をする場合があります。
これらの相続登記申請をすることによって、申請義務は「完全に」履行されたことになります。
一方、上記③の遺産分割をする前に、「とりあえず」法定相続分の登記を申請することも可能です。但し、この場合は、上記登記後に遺産分割協議をする必要があり、当該協議によって法定相続分を超えて所有権(持分)を取得した相続人は、遺産分割の日から3年以内に更正登記を申請する必要があります。つまり、この方法によった場合、場合によっては再度の登記申請をしなければ申請義務を完全に履行したことにならないので、注意が必要です。
【不動産を相続した場合、どう対応すれば良いですか?】
共同相続人全員の間で早めに遺産分割協議(話合い)を行い、遺産分割協議書(共同相続人全員が署名・押印(個人実印)し、各自の印鑑証明書を添付)を作成し、不動産を取得した場合は、その結果に基づいて法務局に登記申請する必要があります。
次回は、期限までに相続登記をすることが難しい場合の対応策などについてお話しします。
(著者:司法書士 大谷)
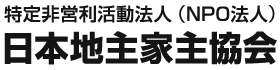

 03-3320-6281
03-3320-6281
