不動産投資…プロとエンドユーザーの違い
物価も不動産価格も永遠に下がらないと皆が信じて疑わなかった1980年代後半の不動産バブルの崩壊によって、不動産価格も物価もいろんな要因によって上がったり下がったりするということがわかり、その教訓から、特に不動産投資は不動産の値上り益ではなく、家賃などの安定収入に重きを置いた収益力が不動産の価値を決めるという事がもはや常識となりました。

収益不動産を対象とした過度な相続対策による税務トラブルや、金融機関の不正融資など、取引の加熱とともに問題も生じつつも、それでも不動産取引の現場では、本業以外の副収入や老後の年金替わり、楽々家賃収入、資産形成、はたまた、早期リタイアメントなどという魅力的なセールストークによって収益不動産の売買は好調です。いうまでもなく収益不動産売買の指標は物件から得られる収益を基準とした利回りです。
現在の不動産投資は値上がり益期待ではなく、収益力期待であるということは前述したとおりですが、それはあくまでエンドユーザーでの視点です。
では、不動産のプロである不動産業者はどうかというと、今も昔も変わりなく値上がり益重視なのです。
かつては世の中の流れによって土地価格そのものが上昇し、そこで値上がり益を得ておりましたが、収益価格重視の現在は、利回りの差によって値上がり益を得ているのです。
例えば年間賃料収入1000万円の物件を利回り8%である12,500万円にて購入し、利回り6%の16,666万円で売却できれば値上がり益(転売益)は4,166万円です。
仮に利回り4%で売却できれば、なんと、倍の25,000万円です。
このように収益価格に着目すると、利回り1%の差によって不動産価格に大きな影響を与えることがお分かりいただけると思います。
この考え方では周辺の土地相場や賃料相場、土地価格や賃料の増減は価格に大きな影響を受けず、物件の個別性や取引相手の個別性が非常に強くなります。不動産のプロは利回りが何%であればエンドユーザーが購入するかを想定したうえで、いくらで物件を購入するかが値上がり益を享受するための重要なポイントになっています。
このような取引の流れや仕組みを考えますと、エンドユーザーはその名の通り、最終消費者であって、最終消費者であるがゆえに不動産の値上がり益は、そもそも期待する立場にはない。という悲しい現実を知ることができます。
とはいいながら適正価格、適正利回りで購入しなければ、特に借入金を活用する場合は安定した賃貸経営はできません。
(著者:不動産コンサルタント 伊藤)
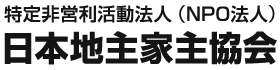

 03-3320-6281
03-3320-6281
